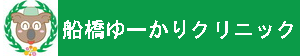亜鉛探訪No.043
白髪と亜鉛
〜メラノサイトと酸化ストレスの物語〜
ある日、鏡を見て「白髪が増えたかも?」と感じたことはありませんか。白髪は“年齢のサイン”のように思われがちですが、実は細胞の環境や栄養状態にも深く関係しています。今回は、髪の色をつくる「メラノサイト」と、それを支える「亜鉛」のお話です。
髪の色をつくる細胞たち
髪の毛は、毛母細胞がつくる「タンパク質の柱」に、メラノサイトがメラニンという色素を渡すことで黒く見えます。つまり、毛母細胞とメラノサイトは“二人三脚”で働いているのです。
ところが、加齢やストレス、紫外線などで酸化ストレスが増えると、メラノサイトの働きが落ちてしまいます。結果、メラニンがつくられなくなり、髪が白くなるのです。
白髪は「酸化ストレス」のサイン
2003年にTobinらが発表した研究では、加齢に伴いメラノサイト内の酸化ストレスが蓄積し、過酸化水素(H₂O₂)が増えることで髪が白くなることが示されました。
Tobin DJ, Paus R. J Invest Dermatol. 2003;119(1):7–13.
これは、体内で“錆びつき”が進むような現象です。活性酸素をうまく処理できなくなると、メラノサイトのDNAが損傷し、色をつくる力が弱まります。
メラノサイト幹細胞と「再び黒くなる可能性」
「白髪は一度できたら元に戻らない」と思われがちですが、最近の研究では一部の毛包では再び黒くなる例も報告されています。
2005年のNishimuraらの論文によると、毛包に残ったメラノサイト幹細胞が環境の影響で再活性化することがあるのです。
Nishimura EK, Granter SR, Fisher DE. Science. 2005;307(5710):720–724.
つまり、「細胞がまだ生きているかどうか」がカギ。残っていれば、毛包の環境を整えることで再び色を取り戻す可能性があります。
亜鉛が支える“細胞の再生力”
ここで登場するのが、私たちのテーマである「亜鉛」です。亜鉛は体内で300種類以上の酵素に関わり、その中にはSOD(スーパーオキシドディスムターゼ)という抗酸化酵素も含まれます。SODは活性酸素を除去し、細胞の酸化ダメージを防いでくれます。
また、亜鉛はDNA修復酵素の補因子でもあり、メラノサイトや毛母細胞の“再生”をサポートします。つまり、白髪を根本から防ぐというよりも、「まだ生きている細胞を守る」働きをしているのです。
食事でとりたい亜鉛
- 牡蠣(かき)
- 牛赤身肉
- 卵黄
- ナッツ類
- レバー
これらの食品には、亜鉛のほかに鉄や銅、たんぱく質も含まれています。バランスよく摂ることが、毛包全体の健康維持につながります。ビタミンC・Eなどの抗酸化ビタミンを合わせると、さらに効果的です。
まとめ:白髪は“細胞の声”
白髪はただの「老化の印」ではなく、細胞からのサインです。髪の色をつくる細胞を守るには、体の中の酸化ストレスを減らし、必要なミネラルを補うことが大切です。
その中でも、亜鉛はまさに“見えない守護神”。
今日の食事に少しだけ「亜鉛」を意識してみませんか?髪も肌も、そして心も、少しずつ元気を取り戻すかもしれません。
参考文献
| 題名 | 白髪:毛包色素ユニットの老年生物学 |
|---|---|
| 文献 | Exp Gerontol. 2001 Jan;36(1):29-54. |
| 抄録 | ヒトの外見は、主に皮膚と髪の色に由来する。この現象の背景にある系統発生的に古い生化学的経路は「メラニン生成(melanogenesis)」と呼ばれ、表皮メラノサイトからのメラニンが有害な紫外線を遮蔽してヒトの皮膚を保護することは明らかであるが、毛髪の色素沈着の生物学的価値はそれほど明確ではない。社会的/性的コミュニケーションにおける重要な役割に加え、ヒトにおける頭髪の色素沈着の潜在的な利点のひとつは、重金属や化学物質、毒素がメラニンに選択的に結合することによって、体外に速やかに排泄されることかもしれない。 |
| 毛包と表皮のメラニン生成システムは、オープンではあるが、大まかに区別される。表皮の連続的なメラニン生成と比較して、毛包のメラニン生成の主な特徴は、毛包のメラニン生成が毛髪の成長サイクルと密接に結びついていることである。このサイクルには、メラノサイトの増殖期(anagen初期)、成熟期(anagen中期から後期)、アポトーシスによるメラノサイトの死滅期(catagen初期)が含まれるようである。したがって、各毛周期は無傷の毛包色素単位の再構築と関連している...少なくとも最初の10周期ほどは。その後、白髪や白毛が現れるが、これは加齢に関連し、遺伝的に調節された、個々の毛包の色素潜在能力の枯渇を示唆している。 |
|
| メラノサイトの老化は、核およびミトコンドリアDNAに対する活性酸素種を介した損傷と、その結果生じる加齢に伴う突然変異の蓄積に関連している可能性があり、さらに細胞内の抗酸化機構やプロ/抗アポトーシス因子の調節障害にも関連している可能性がある。 |
|
| 「白髪」という認識は、色素沈着した毛髪と白髪が混在していることに由来するところが大きいが、個々の毛包が実際に色素の希釈や真の白髪を示すことがあることに注意することが重要である。この色素の希釈は、毛球部メラノサイトのチロシナーゼ活性の低下、メラノサイトと皮質ケラチノサイトの相互作用が最適でないこと、メラノサイトが外毛根鞘上部のリザーバーから毛球の真皮乳頭近くの色素を許容する微小環境へ移動する際の欠陥によるものである。 |
|
| アポトーシス生存因子(bcl-2など)やメラニン生成酵素(TRP-1)に突然変異を起こした動物モデルは、老化する毛髪色素単位について貴重な洞察を与えている。試験管内で毛包のメラノサイトを増殖させることができるようになったことも含め、これらやその他の進歩から、白髪を逆転させる可能性が出てきたのである。実際、初期の無毛症では、同じ毛幹に沿って自然に色素が再形成されることはそれほど珍しいことではない。さらに、白髪や白毛の毛包から採取したメラノサイトは、試験管内で色素沈着を誘導することができる。白髪における色素脱失の驚くべき結果のひとつは、ケラチノサイトの増殖と分化の変化であり、毛包内のメラノサイトが、メラニンのパッケージだけよりもはるかに多くの寄与をしていることを示唆している。 |
|
| さらに、白髪は(因果関係はないものの)骨粗鬆症などより全身的なホメオスタシスの変化と関連している可能性を示唆する未確認の報告もいくつかある。ここでは、ヒト毛包色素ユニットの発達、調節、制御に関する知識の現状について概説する。 |
Tobin & Paus(2001)の要点
1)ヒトの外見と色素の意義
外見は主に皮膚と毛髪の色に由来。表皮メラノサイトのメラニンは紫外線遮蔽で保護的。一方、毛髪の色素沈着の生物学的意義は不明瞭だが、重金属・毒素のメラニン選択的結合による速やかな排泄という利点が示唆される。
2)皮膚と毛包のメラニン生成の違い
両者は開かれた類似システムだが大まかに区別される。表皮は連続的、毛包は毛周期と密接に連動(成長期で活性化、退行期初期にメラノサイトがアポトーシス)。各毛周期で毛包色素ユニットが再構築される。
3)加齢に伴う色素潜在能力の枯渇
およそ最初の10周期の後、白髪・白毛が出現。遺伝的に調節された毛包ごとの色素潜在能力の減衰を示唆。メラノサイト老化には、核/ミトコンドリアDNAの活性酸素種による損傷、加齢変異の蓄積、抗酸化機構やアポトーシス制御の乱れが関与しうる。
4)「白髪」と「色素希釈」の区別
見かけの白髪は、色素毛と無色毛の混在による視覚効果が大きい。ただし、単一毛包でも真の無色化や希釈が起こりうる。機序として:チロシナーゼ活性低下、メラノサイト–皮質ケラチノサイト相互作用の不全、外毛根鞘上部から毛球部へのメラノサイト移動不全など。
5)遺伝子変異モデルからの示唆
bcl-2(アポトーシス生存因子)やTRP-1(メラニン生成酵素)の変異モデルは、老化に伴う毛包色素ユニット崩壊の理解に貢献。メラノサイト生存・機能維持に遺伝要因が関与することを示す。
6)白髪“逆転”の可能性
毛包メラノサイトのin vitro培養が可能になるなどの進歩により、白髪(canities)を逆行させる可能性が提起。初期の無色毛では同一毛幹で自然再色素化が起こる例があり、白髪毛包由来メラノサイトも試験管内で色素沈着を再誘導しうる。
7)白髪化とケラチノサイト動態の変化
白髪ではケラチノサイトの増殖・分化に変化が見られ、メラノサイトが単なるメラニン供給以上に毛包恒常性へ広範に寄与している可能性を示す。
8)全身性老化との関連(仮説)
白髪と骨粗鬆症など全身ホメオスタシス変化の関連を示唆する未確認報告がある(因果は未確立)。白髪が全身状態の指標となる可能性がある。
9)レビューの目的
ヒト毛包色素ユニットの発達・調節・制御の最新知見を概説し、白髪発生機構と可逆性の可能性を総合的に整理する。