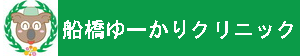亜鉛探訪No.010
牡蠣と亜鉛
『亜鉛探訪010』へようこそ!
亜鉛が一番多く含まれている食材といえば、牡蠣(オイスター)です。なぜ、牡蠣に亜鉛が多く含まれているのでしょうか?そのメカニズムについてご紹介します。なお、多いと言っても、標準的な25gの牡蠣1個に含まれる亜鉛は3.5mg(カロリーSlism参照)ですので、1日亜鉛10mgを摂取したい場合は、牡蠣3個、30mgだと9個食べる必要があります。
1. 亜鉛と牡蠣の関係
なぜ牡蠣に亜鉛が豊富か
| 要点 | 牡蠣は、他の食材と比べても非常に多くの亜鉛を含んでいますが、なぜ牡蠣がここまで亜鉛に富んでいるのかをご存じでしょうか?牡蠣は海水中からミネラルを吸収する特殊な能力を持っており、特に亜鉛の吸収率が高いのです。実は、牡蠣の代謝や成長に亜鉛が欠かせないことがその背景にあります。 |
|---|
2. 牡蠣に含まれる亜鉛
生体利用効率と健康効果
| 要点 | 亜鉛は体内でさまざまな酵素の働きをサポートしますが、牡蠣に含まれる亜鉛は特に生体利用率が高いと言われています。牡蠣を食べることで効率よく亜鉛を補給でき、免疫機能の向上や肌の健康維持に役立つとされています。 なぜ、ヒトの体内への吸収がよいのか? このあと、研究論文からご紹介します。 |
|---|
3. 亜鉛と牡蠣のメカニズム
海洋環境での亜鉛濃縮の仕組み
| 要点 | 牡蠣が海中の亜鉛を効率的に取り込むメカニズムには、金属イオンを取り込むための特殊な輸送体が関与しています。海水中の亜鉛イオンが牡蠣の細胞内に運ばれ、蓄積されることで、牡蠣全体に亜鉛が豊富に分布します。このプロセスは牡蠣の成長に必須で、代謝を活性化する役割を果たしています。 |
|---|
4. 牡蠣由来の亜鉛
効率よく摂取する方法
| 要点 | 亜鉛は体内での吸収が比較的難しいミネラルの一つですが、牡蠣からの摂取はその吸収効率を高めるとされています。料理法や摂取の頻度によっても吸収率が変わるため、日常的に牡蠣を取り入れることで亜鉛不足を予防することが期待できます。 |
|---|
5.牡蠣由来亜鉛が高吸収である理由
| 題目 | 亜鉛キレートを介したプラスチン反応により修飾されたカキ由来の亜鉛結合ペプチドが亜鉛の腸管吸収を促進する |
|---|---|
| 文献 | Mar Drugs. 2019 Jun 8;17(6):341. |
抄録
| 背景 | カキ(Crassostrea gigas)由来の亜鉛結合ペプチドは、亜鉛補給への効果が期待される。 本研究の目的は、プラスチン反応に従って外因性グルタミン酸を添加することにより、カキ改質加水分解物から効率的な亜鉛結合ペプチドを調製し、さらにペプチド-亜鉛複合体(MZ)の亜鉛吸収メカニズムを探求することである。 |
|---|---|
| 結果 | プラステイン反応の最適条件は、pH5.0、40℃、基質濃度40%、ペプシン添加量500U/g、反応時間3時間、l-[1-13C]グルタミン酸濃度10mg/mLであった。 13C同位体標識の結果から、l-[1-13C]グルタミン酸の添加がペプチドの亜鉛結合能の増加に寄与していることが示唆された。疎水性相互作用がプラスチン反応の主な作用機序であった。 紫外線スペクトルと走査型電子顕微鏡(SEM)により、亜鉛結合ペプチドは亜鉛と結合し、MZを形成することが明らかになった。 次に、MZはフィチン酸存在下で、一般的に使用されているZnSO4と比較して、亜鉛のバイオアベイラビリティを有意に高めることができた。 最後に、MZは主に亜鉛イオンチャネルと低分子ペプチド輸送経路の2つの経路を通じて、亜鉛の腸管吸収を有意に促進した。 |
| 結論 | 我々の研究は、MZの亜鉛吸収メカニズムの理解を深め、MZの補助薬としての応用の可能性を支持することを試みた。 |
6.牡蠣肉エキスの鎮痒効果
| 題目 | 牡蠣肉エキスの鎮痒作用(The anti-pruritic effects of oyster extract) |
|---|---|
| 文献 | 東京医科大学雑誌(0040-8905)65巻4号 Page393-400(2007.10) 英語 |
抄録
| 背景 | 慢性腎不全の血液透析患者における皮膚そう痒症 (uremic pruritus) では、血中および表皮中の亜鉛濃度が低下しており、亜鉛補充療法が有効と考えられている。 亜鉛を多く含む牡蠣肉エキス (OE) の鎮痒作用を、アトピー性皮膚炎 (AD) 動物モデルで評価した。 |
|---|---|
| 方法 | 実験1:発痒モルモットモデルでの試験 ヒスタミン (HS) およびカリクレイン (KK) による発痒に対し、OEが鎮痒効果を発揮。主成分であるタウリン、グリコーゲン、有機亜鉛を検討したところ、有機亜鉛 (OZ) のみがKK発痒に有意な抑制効果を示した。 実験2:IgE依存の耳介皮膚炎症反応を伴うマウスモデル (IgE-mIP-ICR) を用いた試験 OEとOZが、刺激物質DNFB塗布後の2時間累積そう痒行動を有意に抑制。同マウスモデルにて、OEとOZが惹起1、24時間後の二峰性皮膚炎症を有意に抑制。同マウスモデルでの累積そう痒行動を1時間の間で有意に抑制した。 |
| 結果 | OEおよびその成分OZが、アトピー性皮膚炎モデルにおいて皮膚の炎症およびそう痒行動の両方を抑制。 OEはAD患者の炎症とそう痒に効果が期待でき、さらに慢性腎不全の血液透析患者の皮膚そう痒症に対しても有効な可能性が示唆された。 |
7.牡蠣に金属が蓄積する仕組み
濾過摂食の過程での吸収
| 要点 | 牡蠣は海水中に含まれる粒子やプランクトンを濾しとって食べる際、亜鉛のような必須ミネラルとともに、カドミウムや鉛、ヒ素などの有害な重金属も一緒に取り込んでしまうことがあります。 特に汚染度の高い海域では、牡蠣が体内に蓄積する重金属濃度が高くなる傾向があります。 |
|---|
メタロチオネインによる結合
| 要点 | 牡蠣は体内で重金属を蓄積する際、メタロチオネインというタンパク質を利用しています。このタンパク質は亜鉛や銅などの有益な金属を結合する役割を果たす一方で、カドミウムなどの重金属とも結合します。 メタロチオネインによって結合されたカドミウムは牡蠣の体内で安全に蓄積され、他の生体成分に対する毒性を一部緩和しますが、やはり摂取する人にとっては健康リスクを伴います。 |
|---|
蓄積部位と濃度
| 要点 | カドミウムは特に牡蠣の肝臓や腸に高濃度で蓄積されることが知られています。これらの部位は、メタロチオネインの濃度が高いため、カドミウムを結合して保持する能力が高いです。 |
|---|
環境の影響と食品規制
| 要点 | 牡蠣の生育環境が重金属汚染されている場合、牡蠣の体内に有害金属が蓄積するリスクが高まります。海域によっては、牡蠣に含まれる重金属の濃度が規定値を超えないようにするための厳格なモニタリングが行われており、食用の牡蠣として流通するものについては安全基準が設けられています。 |
|---|
摂取する際の注意
| 要点 | 日本や欧米では、重金属の濃度が安全基準内に収まるよう牡蠣の生産地や出荷段階での検査が行われています。しかし、過剰な摂取はカドミウムの蓄積リスクを高める可能性があるため、特に妊婦や子供などは適度な摂取量を心がけると良いでしょう。 |
|---|
8.牡蠣に含まれる重金属濃度
牡蠣は他の重金属も貯め込んでいる心配がありましたので、有害な重金属が蓄積していないかどうか、検査結果を参照してみました。
検査機関
有害金属の検査結果
- カドミウム 0.4ppm(平均)
- 鉛・すず 検出せず
- アサリ、ハマグリ、カキなどの重金属は?

この検査結果から有害な重金属は極低濃度で、安心できます。
9.まとめ
牡蠣の持つ亜鉛の力
| 要点 | 牡蠣は単なる美味しい海の幸だけでなく、私たちに豊富な亜鉛を提供してくれる貴重な存在です。日々の食事に牡蠣を加えることで、亜鉛の恩恵を享受し、健康をサポートすることができます。 ご注意:牡蠣アレルギーがある場合は食べないようお願いします。 |
|---|