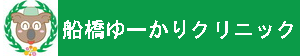亜鉛探訪No.018
糖尿病と亜鉛
『亜鉛探訪022』へようこそ!
亜鉛がインスリンの合成と分泌において欠かせない成分であることは『亜鉛探訪18』で述べましたが、糖尿病の治療にも応用できるのでしょうか?糖尿病と亜鉛の関係についてさらに詳しく解説します。
糖尿病と亜鉛の関係 – インスリンの影の主役?
| 要点 | 糖尿病は 膵臓のβ細胞 でのインスリン分泌異常が主な原因ですが、その裏には 亜鉛(Zn²⁺) という重要なミネラルの存在があります。膵臓の β 細胞では、インスリンの分泌を調節するために亜鉛が必要不可欠です。 糖尿病患者では膵臓内の亜鉛が 75% 減少する ことが報告されています。また、血清亜鉛レベルが低下し、尿中への亜鉛排泄量が増加することも分かっています。 |
|---|
亜鉛と糖尿病リスクの関係
| 要点 | 近年の遺伝子研究により、ZnT8 という亜鉛トランスポーターの遺伝的変異が 2 型糖尿病の発症リスクに関与している ことが判明しました。ZnT8 の変異により、インスリンの安定性が低下し、分泌異常を引き起こす可能性 があります。 |
|---|
亜鉛は糖尿病治療に役立つのか?
| 要点 | 亜鉛には インスリンの作用をサポートする機能 があります。実際に、亜鉛を補充することで HbA1c が改善し、インスリン分泌が安定する可能性が報告されています。特に、遺伝的に ZnT8 の活性が低い人では亜鉛補充の効果が高い可能性 があります。 しかし、亜鉛補充が すべての糖尿病患者に有効とは限らない ため、個々の体質や遺伝情報を考慮した治療が必要です。 |
|---|
まとめ
- ✔ 亜鉛はインスリンの分泌と貯蔵に不可欠
✔ 糖尿病患者では血清亜鉛濃度が低下し、膵臓内の亜鉛も減少
✔ ZnT8 の遺伝的変異が糖尿病リスクに関与
✔ 亜鉛補充は一部の糖尿病患者で症状改善の可能性あり
参考文献2
| 題目 | 亜鉛と糖尿病 |
|---|---|
| 文献 | Arch Biochem Biophys. 2016 Dec 1:611:79-85. |
抄録
| 概説 | 亜鉛2+イオンはインスリンの正常な処理と貯蔵に必須であり、膵臓のインスリン含量の変化はすべての糖尿病と関連している。 過去10年間の研究により、2型糖尿病のリスクに影響する遺伝子として、膵島β細胞およびα細胞の分泌顆粒に高選択的に発現する亜鉛トランスポーターZnT8をコードするヒトSLC30A8遺伝子の変異が同定された。 ここでは、膵島細胞における亜鉛2+イオンの制御と役割、SLC30A8変異体がグルコースホメオスタシスと糖尿病リスクに影響を及ぼす可能性のあるメカニズム、そしてこれらの疑問を探るために開発された組換え標的亜鉛プローブやノックアウトマウスなどの新しい技術について概説する。 |
|---|
要約
1. 亜鉛と糖尿病の関係
| 要約 | 亜鉛(Zn²⁺)はインスリンの処理と貯蔵に不可欠であり、膵臓のインスリン含有量は糖尿病のすべてのタイプに影響を受ける。 遺伝的研究から、**SLC30A8 遺伝子(亜鉛トランスポーター ZnT8 をコード)**の変異が 2 型糖尿病(T2D) のリスクに影響を与えることが明らかになった。 |
|---|
2. 糖尿病患者と亜鉛の関係
| 要約 | 糖尿病患者の膵臓では亜鉛含有量が 75% 減少 する。 1 型糖尿病(T1D)および 2 型糖尿病(T2D) の患者では 血清亜鉛濃度が低下 し、尿中への排泄量が増加する。 亜鉛には 抗酸化作用 があり、酸化ストレスを軽減する可能性がある。 動物実験およびヒトの臨床試験 では、亜鉛補充が T2D の症状改善に寄与することが示されている(HbA1c 減少、コレステロール改善)。 |
|---|
3. 膵臓 β 細胞における亜鉛の役割
| 要約 | 健康な膵臓は亜鉛を 高濃度 に含み、特にβ細胞に豊富に存在する。 亜鉛はインスリンの貯蔵と放出に不可欠 であり、ZnT8 によって分泌顆粒へ輸送される。 ZnT8 が変異すると、インスリンの安定性が低下し、糖尿病リスクが増加する可能性がある。 |
|---|
4. ZnT8 と糖尿病リスク
| 要約 | ゲノムワイド関連解析(GWAS) により、ZnT8 の遺伝的変異(R325W 変異)が糖尿病リスクに関連することが確認された。 ZnT8 欠損マウス では グルコース代謝異常、インスリン貯蔵の減少、インスリン放出の異常 が観察される。 ZnT8 の機能低下は 肝臓でのインスリン分解を抑制し、インスリン作用を強化する 可能性がある。 |
|---|
5. 亜鉛の分泌とインスリン標的組織への作用
| 要約 | インスリン分泌時に放出される亜鉛は 膵臓β細胞に対する負のフィードバック作用 を持ち、インスリン分泌を調節する。 亜鉛は α細胞のグルカゴン分泌を抑制 する。 脂肪細胞や筋肉細胞 において、亜鉛はインスリン受容体のリン酸化を促進し、インスリンの作用を模倣する。 |
|---|
6. まとめと臨床応用
| 要約 | ZnT8 の活性を調節することは、糖尿病治療の新たな標的となる可能性がある。 個別の遺伝的背景 に基づいた パーソナライズド治療(例:亜鉛補充の有効性の個人差)が求められる。 |
|---|
参考文献1
| 題目 | 亜鉛と糖尿病:分子メカニズムの解明と臨床的意義 |
|---|---|
| 文献 | Daru. 2015 Sep 17;23(1):44. |
抄録
| 背景 | 糖尿病は、世界的に罹患率と死亡率の主要な原因となっている。 亜鉛は1型糖尿病と2型糖尿病の両方に多くの有益な効果をもたらすことが研究により示されている。 我々は、血糖コントロール、β細胞機能、糖尿病の病態とその合併症に対する亜鉛のメカニズムと分子レベルの効果に関する文献を評価することを目的とする。 |
|---|---|
| 方法 | PubMedおよびSciVerse Scopusの医学データベースにおいて、論文タイトル、抄録またはキーワードに以下の検索語を用いて、糖尿病における亜鉛の作用機序を報告した発表研究のレビューを行った;(「亜鉛」または「Zn」)および(「機序」または「作用機序」または「作用」または「効果」または「病態」または「生理学」または「代謝」)および(「糖尿病」または「糖尿病前症」または「糖」または「グルコース」または「インスリン」)。 |
| 結果 | 文献検索により、PubMed(n=1799)およびSciVerse Scopus(n=1879) の2つのデータベースで以下の論文数が同定された。 重複を除いた結果、本総説に含まれる論文数は111であった。 その結果、亜鉛はβ細胞機能、インスリン作用、グルコースホメオスタシス、糖尿病およびその合併症の病因において重要な役割を果たしていることが示された。 |
| 結論 | 多くのin-vitroおよびin-vivoの研究により、亜鉛は1型糖尿病および2型糖尿病のいずれにおいても有益な効果を示すことが示されている。 しかし、ヒトにおける治療安全性を確立するためには、適切な期間実施された無作為二重盲検プラセボ対照臨床試験がさらに必要である。 |