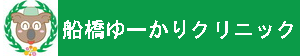亜鉛探訪No.034
白皮症と亜鉛
『亜鉛探訪034』へようこそ!
私たちの肌や髪、目の色は「メラニン」と呼ばれる色素によって決まっています。このメラニンを作るうえで大切な役割を果たすのが、「チロシナーゼ」という酵素です。実はこの酵素のはたらきには、銅や亜鉛などのミネラル亜鉛イオンが関わっています。なかでも、チロシナーゼによく似たタンパク質「TYRP1」には、2つのタイプが含まれていることが近年の研究で明らかになっています。TYRP1がうまく機能しないと、**生まれつき色素が作れない「白皮症(アルビニズム)」**という状態になることがあります。一方で、大人になってから一部の皮膚が白くなる「白斑(はくはん)」は、別の仕組みで起こるものです。亜鉛はこうした色素や酵素の働きを支える、大切な栄養素のひとつ。私たちのからだの中で、さまざまな酵素のサポート役をしてくれています。色素の悩みがあるとき、体の内側からのケアとしてミネラルバランスを整えることも、選択肢のひとつになるかもしれません。
1.チロシナーゼとは
| 要点 | メラニン生合成系は、皮膚・毛髪・眼の色素形成を担う重要な経路であり、その中心的な酵素がチロシナーゼ(tyrosinase)である。チロシナーゼは銅依存性酸化酵素であり、チロシンからDOPA、DOPAキノンを経てメラニンへ至る初期段階を触媒する。一方、チロシナーゼ様タンパク質群であるTYRP1(Tyrosinase-Related Protein(チロシナーゼ関連タンパク質))およびTYRP2も、メラノソーム内で機能的に連携しながら色素形成に関与している。 |
|---|
2.TYRP1遺伝子変異と白皮症
| 要点 | 近年のX線結晶構造解析により、TYRP1の活性中心には従来想定されていた銅ではなく2つの亜鉛イオンが配位していることが明らかとなった。これにより、TYRP1は酸化還元酵素活性を有さず、むしろ構造的安定性や他酵素との相互作用を通じた間接的な調節因子としての役割を担っている可能性が示唆されている。 実際、TYRP1遺伝子の変異は**眼皮膚白皮症3型(OCA3)**の原因となりうることが報告されており、その多くはタンパク質の折りたたみ不全や細胞内局在異常に起因するとされている。このことから、活性中心の亜鉛イオンは酵素活性というよりも、タンパク質構造の安定化において不可欠な因子であると考えられる。 |
|---|
3.白皮症と白斑症は異なる病態
| 要点 | 一方で、後天性の色素脱失疾患である**尋常性白斑(vitiligo)**は、自己免疫機序を背景にメラノサイトが破壊される疾患であり、遺伝性の白皮症とは病態が異なる。しかし、亜鉛欠乏がメラノサイトの脆弱性や酵素の機能不全を助長する可能性もあり、微量元素バランスが色素異常の発症・進展に与える影響については、今後の検討課題である。 |
|---|
4.結論
| 要点 | チロシナーゼ関連酵素群における亜鉛の存在は、メラニン代謝系における新たな視点を提供する。特にTYRP1の亜鉛結合構造は、遺伝性白皮症の分子病態解明および治療標的の探索において注目される領域であり、さらに栄養学的側面からのアプローチも含めた統合的理解が求められる。 |
|---|
参考文献2
| タイトル | ヒト型チロシナーゼ関連タンパク質1の構造から、メラニン生成に重要な二核亜鉛活性部位が明らかになった |
|---|---|
| 文献 | Angew Chem Int Ed Engl. 2017 Aug 7;56(33):9812-9815. |
抄録
| 背景 | チロシナーゼ関連タンパク質1(TYRP1)は、ヒトのメラノサイトに存在する3つのチロシナーゼ様糖酵素のうちの1つであり、皮膚、眼、毛髪の色素沈着の原因となる化合物であるメラニンの産生に重要な役割を果たしている。 これらの酵素を純粋な形で生産することは困難であり、その活性や、アルビニズムや色素沈着障害を引き起こす突然変異の影響についての理解を妨げてきた。 |
|---|---|
| 目的 | 今回我々は、TYRP1の典型的なチロシナーゼ様サブドメインが、チロシナーゼに見られる銅イオンの代わりに2個の亜鉛イオンを活性部位に含んでいることを示し、TYRP1がチロシナーゼ酸化還元活性を示さない理由を説明した。 |
| 結果 | さらに、脊椎動物のメラニン生成タンパク質に特有なCysリッチサブドメインが、上皮成長因子様フォールドを持ち、チロシナーゼサブドメインと強固に結合していることが、構造から初めて明らかになった。 |
| 結論 | われわれの構造から、アルビニズムに関連するTYRP1の変異のほとんどが、その安定性や活性に影響を及ぼすことが示唆される。 |
参考文献1
| タイトル | OCA3に関連するTyrp1変異体:タンパク質の安定性とリガンド結合の計算論的特性評価 |
|---|---|
| 文献 | Int J Mol Sci. 2021 Sep 22;22(19):10203. |
抄録
| 背景 | 眼皮膚アルビニズム3型(OCA3)は、TYRP1遺伝子の変異によって引き起こされる常染色体劣性疾患である。 チロシナーゼ関連タンパク質1(Tyrp1)は、5,6-ジヒドロキシインドール-2-カルボン酸オキシダーゼ(DHICA)から5,6-インドールキノン-2-カルボン酸(IQCA)への酸化を触媒し、ユーメラニン合成に関与している。 |
|---|---|
| 方法 | ここで初めて、Tyrp1タンパク質の安定性と触媒活性を理解するために、OCA3の原因となるTyrp1の4つの変異、C30R, H215Y, D308N, R326Hを計算機的に調べた。 Tyrp1の結晶構造(PDB:5M8L)を用いて、変異タンパク質の安定性を評価するためにグローバル変異誘発を行った。 フォールダビリティーのパラメーターと一致して、C30RとH215Yはより大きな不安定性を示すはずであり、他の2つの変異体、D308NとR326Hはネイティブなコンフォメーションを保つと予想される。 |
| 結果 | 精製した組換えタンパク質のSDS-PAGEとウェスタンブロット分析により、フォールダビリティパラメーターがタンパク質の安定性に重要な変異の影響を正しく予測することが確認された。 さらに、変異体構造を構築し、100ナノ秒のシミュレーションを行い、自由エネルギーランドスケープを作成し、ドッキング実験を行った。 Y362、N378、T391によって形成された自由エネルギー景観は、C30RとH215Y変異体の結合クレフトが野生型Tyrp1よりも大きいことを示している。 |
| 考察 | ドッキングシミュレーションでは、活性部位でDHICAを安定化する水素結合と塩橋相互作用は、Tyrp1、D308N、R326Hの間で類似している。 しかし、これらの相互作用の強さとドッキングされたリガンドの安定性は、変異体では結合クレフトが大きく、あまり明確でない性質のため、変異の程度に比例して減少する可能性がある。 |
| 結論 | アンフォールドしていない変異体における変異の摂動は、活性部位にアロステリックな変化をもたらし、タンパク質-リガンド相互作用の安定性を低下させるかもしれない。 |

| 説明 | Tyrp1結晶構造における各OCA3変異体の位置(5M8Lの鎖A)。 C30、C41、および対応するジスルフィド橋は緑色で、H215はマゼンタ色で、D308はシアン色で、R326は紫色で、ZnAとZnBは灰色の球で示されている。 |
|---|