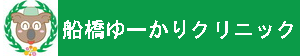🌿 アトピー皮膚炎
原因・特徴
- 保湿たんぱく質 フィラグリンの異常による皮膚バリア障害
- IgE抗体を誘導しやすい体質
標準治療+日常ケア
- ガイドラインに基づく標準治療 新薬で治療法に大変革が起きています
- +食生活の見直し
- +添加物や農薬に注意⇒腸の健康を!
- +肌を擦りすぎない、洗いすぎない工夫
🌿 アトピー性皮膚炎とは
📖 語源
「アトピー」という言葉は1923年、コカ (Arthur F. Coca) と クック (Robert A. Cooke) によって命名されました。
ギリシャ語 「アトポス (atopos)」 =「特定されない」(a=否定、topos=由来)が語源です。
コカ博士は The Journal of Immunology の創設者であり、食物アレルギー検査として「脈拍テスト」を発表しました。
🩺 アトピー性皮膚炎とは
皮膚バリア機能が低下し乾燥しやすく刺激に弱い敏感肌となる状態。
かゆみのある湿疹がよくなったり悪くなったりを繰り返します。
主な要因には、保湿タンパク質フィラグリンの産生異常やIgE抗体を産生しやすい体質(アトピー素因)が挙げられます。
🎯 治療ゴール
治療の最終目標はアトピー性皮膚炎の完治です。しかし重症例では完治が難しい場合も多いため、実際の治療ゴールは症状を落ち着かせ、悪化を防ぎ、日常生活で意識しなくてよい肌状態を維持することです。
発生原因と増悪因子
🔹 内因
- 表皮角質層のフィラグリン機能低下
- IgE抗体を作りやすい体質
🔹 外因(症状を憎悪させる要因)
- 細菌:常在菌の表皮ブドウ球菌
- 真菌:常在菌のマラセチア
- ダニ:ハウスダストの主成分、アレルギーが非常に多い
- ウイルス:イボの発生も多い
- 紫外線:悪化因子
- 汗に含まれる電解質:ナトリウム
- 汗に含まれる微量金属:大豆やチョコに含まれるニッケルなど
- アレルギー食品:卵、乳製品、小麦粉などがIgG産生に関与
- 糖分過剰:糖がタンパク質に結合した最終糖化産物AGESが受容体RAGEに結合して炎症性サイトカイン放出
- トランス脂肪酸:マーガリンに注意、慢性炎症の原因
- 食品や歯磨きに含まれる種々tの添加物:腸粘膜に慢性炎症を引き起こす可能性
🩸 アトピー性皮膚炎の血液マーカー
TARC(ターク)は、アトピー性皮膚炎の炎症の程度を採血で調べる検査で、治療効果の判定にも使用されます。
TARCは「Thymus and Activation-Regulated Chemokine」の略(正式名:CCL17)。
白血球を引き寄せるケモカインの一つで、Th2細胞を病変部に誘導し、IgE抗体や好酸球を活発化させ、かゆみや赤みを引き起こします。
🔢 正常値(pg/ml)
- 小児(6~12ヶ月):1367未満
- 小児(1~2歳):998未満
- 小児(2歳以上):743未満
- 成人:450未満
📊 重症度判定の目安
成人
・700pg/ml未満:軽度
・700pg/ml以上:中等症以上
小児
・760pg/ml未満:軽度
・760pg/ml以上:中等症以上
💰 検査費用:3割負担で1,032円
IgEアレルギー検査(保険適用)
✅ 個別では13種類まで検査可能
対象:花粉、真菌、ダニ、動物、食物など
✅ View39では、13種類の検査価格で 39種類まとめて検査可能なおトクなプランです。
検査費用(3割負担)
約 5,000円
IgG食物アレルギー検査
※当院では実施しておりません
★ ご希望の方は 市販検査キット をご利用ください。
✅ 慢性アレルギーに関係するとされる100品目の食品に対するIgG抗体を調べられます。
検査費用(自費)
35,000円 ~ 50,000円
🌿 日常生活習慣の見直し
🚫 減らすべき食事
- 甘いお菓子(駄菓子、ケーキ、チョコ)
血糖値上昇 → インスリン増加 → 中性脂肪増加 - 炭水化物(ご飯・パン・麺類)
血糖値上昇 → 中性脂肪増加 - 脂っこい食品(カレー、唐揚げ、中華など)
オメガ6・トランス脂肪酸が炎症を助長 - 牛乳・卵・小麦粉
慢性アレルギー(IgG)が関与することがあります
☆ オメガ6脂肪酸の摂取を減らすことで改善した報告あり: 下田妙子. 九州女子大学紀要 第37巻2号
🍽️ 増やすべき食事
- タンパク質(肉・魚・卵・豆腐・納豆)
1日60g以上、可能なら120gを目標に。皮膚修復に必須。 - オメガ3脂肪酸(サバ、サンマ、亜麻仁油、エゴマ油)
炎症を抑制。加熱せず摂取が理想。サバ缶・サンマ缶もおすすめ。 - ココナッツ・MCTオイル
酸化に強く、エネルギー効率が高い。炒め物にも◎。 - ビタミン・ミネラル
ビタミンD(きくらげ・干し椎茸)/C(柑橘)/B(豚肉)
🌿人気のオメガ3/6ブレンドオイル
亜麻仁だけでなく、ひまわり、胡麻、米胚芽、米ふすま、オーツ麦芽胚、オーツ麦ふすま、ココナッツオイル、月見草油、大豆レシチンなど、10種類以上の天然オイルをブレンドした高品質なオイルです。
製造国:カナダ
製法:低温圧搾(コールドプレス)
品質保持:冷凍輸送・冷凍保管・遮光瓶・窒素封入
製造から輸送まで徹底した酸化対策を行い、オメガ3/6脂肪酸を新鮮なまま保っています。
オメガ3脂肪酸は炎症を抑える働きがあり、アトピー性皮膚炎などの皮膚トラブルの改善に役立つとされています。
食事から取り入れることで、肌バリアや免疫バランスのサポートにもつながります。
下記リンク先から直接ご購入ください。
🛁 入浴のポイント
熱いお湯・長湯・洗いすぎに注意。皮脂を落としすぎると乾燥が悪化します。
- 湯船で軽く手のひら洗いで十分
- ボディソープや石鹸は週に数回でOK
🧹 ダニ対策
- こまめな掃除
- ダニ捕りマットの活用
- 布団・カーペットの清潔維持
💊ダニ舌下免疫療法
ダニ抗原を希釈した舌下錠を毎日服用し、体を少しずつ慣らしていく治療法です。
すぎ花粉症がない方、または軽い方で、ダニアレルギーが強い方が対象となります。
🔹使用薬:ミティキュアダニ舌下錠
🔹開始量:低用量 3,300 JAU
🔹維持量:高用量 10,000 JAU
服用後、口の中の腫れや喉のイガイガ感などの副反応がなければ、徐々に高用量へ移行します。
季節性のスギ花粉症に比べて、ダニアレルギーの舌下免疫療法では副反応がやや多く見られる傾向があります。
JAU(Japanese Allergy Units)は、日本アレルギー学会が定めたアレルゲン活性単位です。
「コナヒョウダニ」と「ヤケヒョウダニ」のアレルゲンエキス 22.2〜66.7μg/mLを含むものを 100,000 JAU/mLと定義しています。
💉新しい注射薬
アトピー性皮膚炎では、バイオ製剤(抗体医薬)と呼ばれる注射薬を使用することがあります。
これらは炎症やかゆみを引き起こすサイトカイン(免疫物質)を抑えることで、症状を改善します。
💠 デュピクセント
化学名デュピルマブ(商品名デュピクセント)は、IL-4とIL-13の活動を阻害する抗体薬で、月2回皮下注射で投与します。
アトピー性皮膚炎の炎症反応を抑える治療薬です。当院で実施していません。

🌿 ミチーガ
化学名ネモリズマブ(商品名ミチーガ)は、IL-31の活動を阻害する抗体薬で、月1回皮下注射で投与します。
アトピー性皮膚炎および結節性痒疹に適応があります。当院で実施しています。

💊 内服治療
抗ヒスタミン剤(1日1回)
かゆみや炎症を抑える目的で使用します。眠気の少ない新薬もあります。
- 商品名 (化学名)
- ルパフィン (ルパタジンフマル)
- デザレックス (デスロラタジン)
- ビラノア (ビラスチン)
- ザイザル (レボセチリジン)
- クラリチン (ロラタジン)
- アレジオン (エピナスチン)
抗ヒスタミン剤(1日2回)
- タリオン (ベポタスチン)
- アレグラ (フェキソフェナジン)
- アレロック (オロパタジン)
セレスタミン(配合剤)
ステロイド+抗ヒスタミン剤の配合薬。現在、処方していません。
腫れ止め(トランサミン)
炎症による赤み・腫れ・色素沈着を改善します。
適応:湿疹性紅斑など
漢方薬
体質改善や皮膚の再生を助ける目的で用います。
- 当帰飲子(とうきいんし)
- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
服用:1日3回 食前
抗生物質
掻き壊しなどで細菌感染が起きた場合に使用します。
- フロモックス
- クラビットなど
ビタミンC(サプリメント)
皮膚の回復を助け、色素沈着を抑制します。
サプリメントのビタミンC 1回1gを1日2〜3回内服を推奨。当院では高濃度ビタミンC点滴(自費)をご提供しています。
亜鉛(サプリメント)
皮膚の炎症や色素沈着を抑制します。
サプリメントの亜鉛1回10mg~15mgを1日2〜3回内服を推奨。当院では定期的な採血検査で亜鉛の血中濃度を測定しています。
外用薬(塗り薬)
☆ ω3脂肪酸を含む青魚の缶詰などを定期的に食べるような食生活の改善に取り組みながら外用すると治りやすくなります。
何も変えなければ、塗り薬を止めるとすぐ再発します。
★ 保湿を行いながら、かゆみ止めを使います。
☆ 大人の方で広範囲に塗る必要がある場合は、混合軟膏を処方しています。
☆ お子さんは食事やダニ対策を行い、保湿して、抗ヒスタミン剤を内服しても痒ければ、ステロイドを塗布するという具合に、混合軟膏ではなく、 保湿とステロイドを別々に使う ことでステロイドの使用量を減らしています。
⚠ ステロイドの長期使用は注意が必要です。
皮膚が薄くなり、皮下の血管が透けて見えるようになることがあります。
なるべくステロイドではないかゆみ止めを使用するようにしましょう。
新しいかゆみ止めとして、ブイタマクリームやモイゼルト軟膏、コレクチム軟膏も試してみると良いです。
時に灼熱感が生じるプロトピック軟膏より使いやすい場合があります。
ブイタマクリーム(タピナロフ)
2024年に登場した新しい外用薬で、AHR(アリル炭化水素受容体)経路を活性化することにより、 炎症を抑え、皮膚バリア機能を整える作用があります。
従来のステロイド外用薬やプロトピック・コレクチムとは異なる新機序で、長期的に皮膚の質を改善することが期待されています。
かゆみを和らげ、角層の水分保持・脂質バランスを整えることで、慢性的なアトピー性皮膚炎のコントロールをサポートします。
特徴:
・非ステロイド系/非免疫抑制系の新機序外用薬
・AHR経路活性化による抗炎症・皮膚バリア改善作用
・生物学的製剤未到達部位への追加治療としても有用
・軽度の刺激感や頭痛などがまれに報告されています
剤形:クリーム
開発企業:日本皮膚科学会ガイドライン2024で位置づけが明確化
モイゼルト軟膏
新しいタイプのかゆみ止めです。
プロトピックに比べて灼熱感が少なく使いやすいのが特徴です。
剤形:軟膏
コレクチム軟膏
モイゼルトと同様に非ステロイド系のかゆみ止めです。
タクロリムス(プロトピック)とは作用機序が異なり、より刺激感が少ない傾向があります。
剤形:軟膏
ヘパリン類似物質(保湿剤)
皮膚の乾燥を防ぎ、バリア機能を高めます。
- ヒルドイド
- ビーソフテン
- 後発品多数
剤形:軟膏 / クリーム / ローション / スプレー / 泡フォーム
塗布回数:1日2回
ステロイド(ウィーク〜ミドル)
- ウイーク:ロコイド、アルメタ
- ミドル:リンデロン、リドメックス
剤形:軟膏 / クリーム / ローション
塗布回数:1日2回
⚠ 長期連用で皮膚が薄くなる可能性があります。
ステロイド(ストロング)
- マイザー
- アンテベート
- ネリゾナ
剤形:軟膏 / クリーム / ローション
塗布回数:1日2回
⚠ 強力なため、長期使用には注意が必要です。
タクロリムス(プロトピック)
免疫を抑えて炎症を鎮める薬です。
Tリンパ球の抑制作用があり、皮膚が薄くならない利点があります。
剤形:小児用 / 大人用
塗布回数:1日2回
- 時に灼熱感を伴うことがあります
- 妊娠時は使用できません
- ウイルス感染には注意が必要です
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
すり傷・切り傷の治療やケアについて、
ご不明な点がございましたら、 無料メール相談からお気軽にご相談ください。